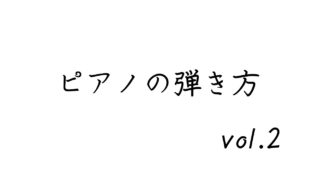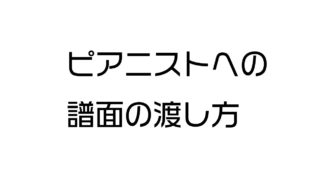先日のリサイタルを聴きに来てくださった皆様、ありがとうございました!
本番でしかわからないことがある。
どんなにホールの響きを想像して練習したり、聴衆が演奏中に出す音などに慣れたとしても、
その本番で聴いてくださっている人がどんな心の反応をして、それをどう自分が感じ取るか、というところは本番でしか味わえない。
「ここで、この音色を出したら空間を伝わってお客さんの反応が来るはずだ。」
なんて、人の反応すらコントロールできると傲慢になっていたら、
全く反応が返ってこなくて焦っちゃう…ということがある。
気にしなければ良いのだけれど、
鈍感過ぎても音楽家にはなれないし、
敏感過ぎると演奏が危うくなる。←これはただの練習不足だけど
いつでも自分を冷静に見つめてるもう一人の自分を作らないと。
敏感に感じ取りつつも、その時起こったことをそれ以上でもそれ以下でもなく、そのものとして受け入れていくように。
14歳の時の本番で初めて
時間と空間を通してお客さんの反応が返って来たのがわかった時に
「これが自分の天職だ。」と腑に落ちたのだけれど、
それまでは「音楽と自分」だけだったものが、「音楽(作曲家)と自分と聴衆」というものになって、
バランスをとるのが少し難しくなった。
(「バランスとるのが難しい」と感じてるのもきっとただの気にしすぎだと思う。)
以前も書いたと思うけれど、
プレスラー先生や、ロシアンピアノスクールで師事したネルセシアン先生もピサレフ先生も
「呼吸」のように音楽してる。
音楽は彼らの生命そのものという感じ。
自分はまだ「食欲」程度。
多少食べなくても生きていけるレベル。
練習は本当に楽しいことなんだけれど、
年齢を重ねるにつれて他の楽しいことも増えてきて、
どの「楽しみ」を選ぶかの選択をする時に、
音楽を選ぶか、その他を選ぶか。
どちらが良い悪いではなく、どういう選択をするかで人生が作られていくことを最近つくづくと感じる。